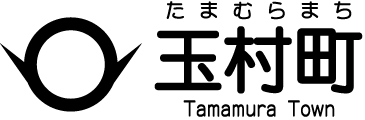公開日 2018年08月23日
更新日 2025年07月31日
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について
クビアカツヤカミキリとは
クビアカツヤカミキリは、平成30年1月15日に外来生物法による「特定外来生物」に指定された外来種の昆虫です。繁殖して樹木を枯死させるおそれがあるため、拡大を防ぐために販売や飼育、運搬などが禁止されています。
玉村町では、クビアカツヤカミキリの被害が多数確認されております。
クビアカツヤカミキリの特徴
| 名称 | クビアカツヤカミキリ(クロジャコウカミキリとも呼ばれる) |
|---|---|
| 原産地 | 中国・モンゴル・韓国・北朝鮮等 |
| 体長 | 成虫は3~4cm(触覚・脚を除く)で、触覚を含めると5~7cm前後となり、カミキリの中ではやや大きい部類。 |
| 特徴 |
・幼虫は白っぽい色。樹木の中に生息し、外からは見られない。 ・成虫は全体的に光沢のある黒色で、胸部(首部)のみ赤く、飛ぶことができる。 |
| 生態 |
・幼虫は樹木内部に寄生し、樹木を食い荒らして木くずと糞の混じった「フラス」を排出する。 ・樹木内部で2~3年かけて成長し、サナギになる。 ・翌年5月中旬~7月に成虫となり、樹木の外に出現する。 ・繁殖力が非常に高く、狭い範囲で大繁殖する傾向がある。 |
| 写真 |
|
クビアカツヤカミキリによる影響
クビアカツヤカミキリは、サクラやモモなどの樹木に寄生し、幼虫が内部を食い荒らすことで樹木を弱らせます。穴が空き、弱った樹木は、水分や養分を運べなくなって枯れてしまい、木が倒れたり枝が落ちたりする危険性があります。
また、日本に本来生息していない生きもの「外来種」であるため、日本に以前から生息している生きもの「在来種」と競合したり、何らかの影響を与える可能性があります。
クビアカツヤカミキリは、在来種のカミキリに比べて、狭い範囲で大量に繁殖するため、被害が速く大きくなる傾向があります。
クビアカツヤカミキリを見つけたら
クビアカツヤカミキリの成虫を見つけた場合は、その場で処分をお願いします。
なお、内部に幼虫がいることが明らかな寄生木を伐採し、運搬することも外来生物法に違反する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592