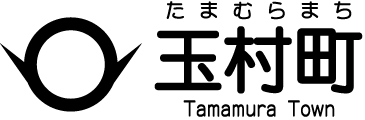公開日 2014年09月24日
村の誕生
新田開発
江戸に幕府が開かれた頃(慶長8・1603)、玉村一帯は100年も続いた戦乱によって荒廃し、中央部には荒涼とした原野が広がっていました。幕府の代官伊奈備前守忠次(いなびぜんのかみただつぐ)は、家臣の江原源左衛門や和田与六郎の協力を得て、荒野に用水を引き新田を開発すると、農民を移住させて集落をつくりました。
「代官堀」(滝川用水)と呼ばれるこの用水の完成によって、玉村の中央部に「新田」という新しい「村」が誕生しました。
玉村八幡宮
江戸時代の初めに誕生した新田村は、その後玉村八幡宮を境にして「上新田村」・「下新田村」の二つの村になりました。玉村八幡宮は、鎌倉時代に鶴岡八幡宮の分身をまつって建てられた角渕八幡宮が移築されたものです。
代官伊奈備前守忠次は、用水工事の成功を角渕八幡宮に祈願し、慶長15年(1610)に角渕八幡宮の建物を新田村の中央部に移築し、修復しました。
玉村八幡宮の規模や格式は県内でも優れたもので、「三間社流造(さんげんしゃながれづくり)」の本殿は、国の重要文化財に指定されています。

玉村八幡宮本殿
玉村八幡宮の祭礼
玉村八幡宮の氏子村は、「玉村七郷」とよばれ、一番村(角渕・上之手)、二番村(上茂木・下茂木・後箇)、三番村(斎田)、四番村(福島)、五番村(南玉)、六番村(上飯島)、七番村(上福島)というように序列がつけられています。祭礼のときには、この玉村七郷によって流鏑馬(やぶさめ)(のちに駆馬(かけうま)・・・6丁目木島本陣前の高札場から八幡宮大鳥居前までを馬を走らせて競うもの)と行列が行われました。
江戸時代後期の藤岡に住み、飛脚問屋に勤め国学に造詣が深かった富田永世(とみたえいせい)の紀行文『ふた道にき』に文政12年(1829)3月の祭礼の様子が記されています。それによると、玉村宿の例幣使道沿いは杉並木になっていて、見世物小屋が建てられ、多くの参詣人で賑わっていたようです。見世物小屋の中では、綱渡り、米俵を持ち上げる怪力女、竹田のからくり人形、曲馬、棒や刀をのむ男、一寸法師などの芸が行われていました。
祭礼は、農民にとっては農業を公然と休める日であり、娯楽の少なかった当時としては数少ない楽しみでもありました。

全景写真
ジオラマ「街道と宿場−例幣使道玉村宿−」
(国立歴史民俗博物館蔵)歴史資料館展示

鳥居から楼門にかけての出店

曲馬

見世物小屋

「玉村八幡宮祭礼図」文政12年(1829)
上之手村の氏子により描かれた絵図。
境内には「玉村七郷」の祭礼具や下新田村
5~9丁目の飾り物が飾られている。
宿場を行き交った人々
日光例幣使
現在、玉村町を東西に抜ける旧国道354号(県道142号線)は、江戸時代、日光例幣使道といわれ、徳川家康をまつる日光東照宮の春の大祭に、京都の朝廷から幣帛を奉納するために派遣される勅使である日光例幣使の一行が通るために整備された道です。
例幣使道は、倉賀野(高崎市)から楡木(にれぎ)(栃木県鹿沼市)に至る道であり、その間には13の宿駅がおかれていました。玉村(玉村町)・五料(玉村町)・柴(伊勢崎市)・木崎(太田市)・太田(太田市)の5宿を経て、下野国(栃木県)に入ります。
明和元年(1764)には、道中奉行の支配となり、五街道につぐ街道として重視されました。
例幣使の派遣は、正保4年(1647)から慶応3年(1867)まで、221年間一度の中断もなく続けられました。例幣使には参議格の公卿が任ぜられ、随員は50~60人ほどでした。一行は、通例毎年4月1日に京都を出発し、中山道、例幣使道を通って、4月15日に日光に到着し、翌16日に東照宮に参拝し、宣命を読み上げ、幣帛を奉納しました。帰路は、江戸に寄り、東海道を通って、京都に戻りました。
五料関所と渡船
五料関所は、五料宿の東北部にある利根川の渡船場に置かれた関所です。全国53の関所中上野国には14の関所がありましたが、このなかでも最も取り締まりの厳しい関所の一つでした。元和2年(1616)幕府により設置されました。
五料関所は、ほかの関所と同様に「入鉄砲に出女」の監視を厳重に行うとともに、利根川の船の監視の役目も担っていました。また、通行手形を以って通し、開門は明け六つ(午前6時)、閉門は暮六つ(午後6時)でした。関所は前橋藩によって管理され、関所役人には、目付1人、番士2人、足軽6人、中間2人がいました。役人の任期が短かったため、五料関所では沼之上村から村役人が出て関所業務を補助しました。また、関所には、鉄砲、槍、犯人捕獲用の三ツ道具(突棒・刺股(さすまた)・袖搦(そでがらみ))などが置かれていました。
五料関所は、日光例幣使の通行があったことも特徴の一つでした。日光例幣使の一行が通る際には羽織袴で土下座をしました。また、日光大祭中は特に交通の取締りが厳しかったようです。
五料の渡船場は幕府が定めた利根川流域16ヶ所の「定船場」の一つでした。渡船の経営は柴宿との共同経営で行われました。船は五料宿から3艘出され、船頭も始め五料宿から3人出ていましたが、明和3年(1766)に、柴宿からも船頭を3人出すことが命じられ、合計6人で渡船にあたりました。文政6年(1823)には、船頭の無作法が原因で船会所を設置し、両宿から役人1名ずつ出て経営するようになりました。現在、関所の名残として、門柱の礎石と古井戸が残されています。
玉村宿・五料宿
玉村宿
玉村宿は、日光例幣使道第一番目の宿場であり、上新田村と下新田村から成り立っています。
宿の全長は約2,610m、道幅は約5mで、4丁目から7丁目にかけて50軒ほどの旅籠屋がたち並び、6丁目に本陣、4丁目と7丁目に問屋場がおかれていました。
玉村宿は、東西に中山道の倉賀野宿から分岐し、壬生(みぶ)道の楡木(にれぎ)に至る日光例幣使道が通り、南北には中山道の本庄宿から玉村、渋川を経て三国街道に出る佐渡奉行街道といわれた三国街道の別路が通る交通の要衝であり、また飯売旅籠屋も数多くたち並び宿場として繁栄しました。しかし、慶応4年(1868)1月11日の大火により、4丁目から9丁目までのほとんどが焼け、本陣もこのとき焼失してしまいました。
例幣使の一行は、毎年4月11日の夕方玉村宿に到着し、翌日早朝には、つぎの宿泊地である天明(てんみょう)宿(栃木県佐野市)を目指して出発しました。
例幣使の通行は、宿場にとっては、入魂料(じっこんりょう)といわれる心付けを強要されるなど宿場を疲弊させる一因にもなりましたが、一方で、人や物資がさかんに行き交い、都の文化が流入し宿場が賑わうといった好影響ももたらしました。
五料宿
現在の玉村町五料は、江戸時代、沼之上(ぬまのうえ)とよばれていました。この村は天正年間(1573~92)には倉賀野との間に伝馬の制度がしかれていたといわれています。この村の東北部の一画が「五料」とよばれていました。
五料の名の由来は、角渕にあった西光寺(現玉村町下新田)の稚児千代寿丸が柴渡船転覆により溺死した、その「御霊」の供養に基づくとされます。また、尾州藩士堀杏庵が寛永13年(1636)に旅したときの日記「中山日録」には、五料という地名は新田義貞の子義興の「御霊」に由来しているという伝承が記されていますが、これは千代寿丸が新田庄出身であることと義興を取り上げた芝居などの影響で、千代寿丸の話が義興の話にすりかえられて伝承流布したのではないかとされる説もあります。
五料宿は玉村宿から東へ1里半(約6km)に位置していました。利根川と烏川の合流点に近く、五料・新・川井の三つの河岸があります。
宿場を支えた人々
※問屋場(といやば)と助郷(すけごう)
宿場の大きな役割の一つは人と荷物の輸送を行うことです。輸送は人馬によって行われたため、宿場にはその人馬を供給する場所として、問屋場が置かれていました。
玉村宿には問屋場が2ヶ所あり、問屋役(問屋場の責任者)は上新田4丁目と下新田5、6、7丁目からそれぞれ2人1組で年番と添番を持ち回りしていました。玉村宿からの継立(つぎたて)(輸送範囲)は、東は五料宿、東南は本庄宿、北は惣社村、西は倉賀野宿と決められていました。玉村宿は「御定人馬(おさだめじんば)」として25人の人足と25疋(ひき)の馬を常備しておくように定められていましたが、実際は「御囲人馬(おかこいじんば)」として5人の人足と5疋の馬のみが常備されていました。しかし、大通行のときなどその人馬だけでは足りないので、近隣の村々から人馬を差し出させていました。これを助郷といい、その村々はあらかじめ割り当てられていました。
一方、五料宿の問屋場は例幣使道の南側で、関所入口の東南に位置していました。問屋役人は始め問屋役2人、年寄1人の3人制でしたが、その後上組、下組の名主2人ずつによる年番制となり、さらに4家による交替制となりました。
※(とんやば)ともいう。
旅籠屋(はたごや)
宿場のもう一つの大きな役割として、旅人へ宿泊施設を提供することがあります。
玉村宿には、日光例幣使など貴人が宿泊する本陣(6丁目木島家)、大通行のときに置かれた臨時の本陣(4丁目井田家ほか)、旅人の給仕をする飯売下女のいる旅籠屋、飯売下女のいない平旅籠屋などがありました。安政2年(1855)には飯売旅籠屋は33軒、平旅籠屋は6軒ありました。
飯売下女は始め、旅人の寝食の世話をすることを役目とされていましたが、しだいに遊女的になり、さらに抱えられている旅籠屋の本業である農業の手伝いもしていました。幕府は宿場が遊郭化するのを防ぐため、旅籠屋一軒につき飯売女は2人までと制限しましたが、これはたびたび破られ、幕府はそのたびに取締りを強化しました。また、宿場の者や近隣の村々の者が飯売旅籠屋の客となることによって風紀を乱すなど問題もありましたが、その一方で、飯売女の存在は玉村宿の繁栄につながるものでもありました。
河岸(かし)
五料・新(しん)・川井の三河岸は、二代将軍秀忠の時代に、前橋藩主酒井氏によって取り立てられたと伝えられています。新河岸は沼田藩の津出し(積み出し)河岸であり、川井河岸は、川の変流によって盛衰はありましたが、三国街道からの荷物のほか、安中米や信州米を扱いました。一方、利根川本流の最上流にあった五料河岸は、筏(いかだ)河岸として木材の輸送で活躍しました。
災害と川の変流
沼之上村(現玉村町五料)では、「卯の泥押」、「午の満水」という言葉で、天明期の災害が語り継がれています。前者は天明3年(1783)の浅間焼けによる泥押し、後者は同6年(1786)の大洪水のことです。
天明3年7月8日(新暦8月5日)、沼之上村とその川下では、昼頃から利根川の水が絶えました。不思議に思いつつも川の中程で魚取りをしていた村人達は、大きな音とともに突然押し寄せた山のような泥流にのみ込まれました。泥流と岩石は、利根川本流の七分川の川口をせき止め、川の流れを変えました。
沼之上村の民家246戸中30戸余りが流失、170戸が埋没し、田畑の90%以上が焼砂に埋まりました。五料関所も泥流により流失、常楽寺は本堂の鴨居の上まで泥で埋まりました。3m以上も積もった焼石と泥によって、五料宿は宿としての機能を失ったのです。前橋藩では、領内の被災した村々に対し米や金を交付し、年貢を減免するなど村民の救済につとめましたが、深刻な被害の前には焼け石に水でした。
さらに追い打ちをかけるように、天明6年(1786)7月、大雨によって利根川が氾濫し、沼之上村の中央を破った新川が烏川に突き抜けました。新河岸の屋敷は流失し、焼石の流入で川底が浅くなり、大きな船が通行できなくなるという河岸として壊滅的な打撃を受ける一方で、船問屋は協力して、川浚(さら)いや税金の免除を幕府や前橋藩に願い出るなど、河岸の復興に努めました。しかし、完全復旧は難しく、移転によって営業を続けた新河岸に対し、烏川の変流も禍した川井河岸は、以降隆盛を取り戻すことはありませんでした。
和泉屋(いずみや)と日野屋(ひのや)
和泉屋(井田家)
和泉屋は井田氏といい、祖先は那波一族とも那波氏の家臣であったとも伝えられています。井田氏は、玉村宿が発展する以前の寛文年間(1661~1673)下之宮村から上新田村に進出しました。
大地主として代々上新田村の名主を勤める一方、例幣使道の整備によって玉村が第1番目の宿場になると、宿場の事務所である問屋場が置かれ問屋役を勤めるようになりました。そして宝永2年(1705)以降、下男、下女約40人を抱える大商人となりました。その規模は、時代により変遷はありますが、一貫して商人として群を抜き、玉村町発展に貢献しました。
商品は、酒や醤油をはじめとする食料品全般のほか、生活用品や薬などあらゆる分野にわたっていました。
小売りは玉村一円を中心としたものでありましたが、仲間取引は前橋・高崎・藤岡・熊谷・本庄・足利など広範囲に及び、さらに地域特産品の問屋として、京都・大坂・江戸の大都市問屋を相手に活動しました。上州の特産品の絹製品は上方へ送られ、京都で関西人の好みに合わせ加工されました。

和泉屋(慶応4年の大火を免れた18世紀初期の建物)
日野屋(瀬川家)
日野屋の古文書に、明和3年(1766)8月、玉村宿下新田村宇兵衛より、日野屋が酒造道具一式を借り受け酒造を始めた記録があります。日野屋は近江国(滋賀県)日野町鎌掛(かいがけ)の出身で、商売の適地として下新田村に出店しました。店は醸造業を中心に、質屋、食品販売、荒物一般を扱いましたが、商品の種類の幅は和泉屋より狭かったようです。
雇人は、番頭以下十数人で、そのほか、蔵人(醸造をする職人)と呼ばれる季節労働者がいました。近江商人の特徴として、主人と雇人は強い同郷意識で結ばれ、主人は雇人を物心両面から援助しました。10歳くらいで店入りすると、読み書き算盤、作法を教えられ、丁稚(でっち)として商売の見習いをしました。忍耐・節約・才覚を身につけ、一生かけて番頭まで登りつめるのです。番頭まで登りつめ定年になると、大部分は国元へ帰り、百姓をして余生を送りました。「のれん分け」を受け支店を出すのは、親戚その他少数の人達でした。
また、日野屋は代々熱心な浄土真宗の信者で、親鸞の教えである「他力本願」を心得としていました。仏の慈悲やお客様への感謝の気持ちは、商売を長続きさせる最高の理念でした。

大正時代の日野屋
和泉屋と日野屋−両家の比較−
和泉屋
- 武士の出身。名主、問屋役、その他種々の役職につき、田畑14町以上所有した大地主。
- 玉村宿に居住し奉公人とともに商売。
- 奉公人は近郷近在から採用し、年季奉公が多い。
- 奉公人は男女問わず使用。
- 店舗と住居が同じ場所。玉村宿で収入を得、消費した。
日野屋
- 主人は国元(近江国)に居住し、年2、3回店へ出張。普段の商売は番頭まかせ。
- 奉公人は国元近江から採用し、終身雇用。
- 従業員は男性のみ。家族を国元に残し単身赴任。
- 店舗のある玉村宿で収入を得、本拠のある国元で消費した。
渡辺三右衛門
渡辺三右衛門陳好(さんえもんのぶよし)は、文化4年(1807)福島村(現玉村町福島)に生まれました。父三右衛門詮季(あきすえ)は、角渕村(現玉村町角渕)名主小屋原佐五右衛門の弟詮勝(あきかつ)の二男で、三右衛門綱忠の長女に迎えられましたが、長女が早世したので後妻を迎えました。その長男が三右衛門陳好です。初代の三右衛門重綱は箕輪(みのわ)城主長野氏に仕え、その後浪人となり福島村に帰農しました。陳好は9代目となります。
三右衛門は、初め南玉村(みなみたまむら)(現玉村町南玉(なんぎょく))町田四郎右衛門の二女を妻として迎えましたが、早世したので、角渕村高橋武左衛門の長女美紀(みき)を後妻に迎え、天保元年(1830)には長男半六好直(はんろくよしなお)が生まれました。
父も福島村の名主役を勤め、三右衛門も若くしてその役を勤めました。日記をつけ始めた36歳時分は組頭を勤めていました。弘化3年(1846)には玉村宿外24ヶ村改革組合村(文政10年に幕府により関東全域に悪党の取締や防犯の強化のために編成された組織)の大惣代(おおそうだい)となり慶応2年(1866)に罷免されるまで20年間勤めました。
玉村宿外24ヶ村改革組合村には福島村も属していました。福島村は、旗本の大久保氏(295石)と島田氏(597石)の二人の領主により支配され、家数は全体で39軒、人数は223人で三右衛門は大久保氏の支配に属していました(慶応2年)。
明治25年(1892)、三右衛門は86歳で亡くなりました。戒名「厚徳院宝満仁英好翁居士」。
三右衛門日記(群馬県指定重要文化財)
「三右衛門日記」は表題には主に「御用私用掛合答其外諸日記」、「御用私用年中諸日記」とあります。日記は、天保13年(1842)12月28日から始まり、明治2年(1869)10月18日までの27年間つけられました。三右衛門36歳から63歳までの日記です。

三右衛門日記にみる年賀
日記にみる三右衛門の正月は、元日に家族とともに鎮守氏神へ参詣し、村方一同(福島村)の年礼を受けます。その後、村年礼に出掛け、2日以降、福島村以外の知人宅をまわるのがほぼ定例でした。年始客には、吸物や酒、そばや雑煮などが振舞われることもありました。
年賀の訪問はふつう1日~3日、町家などでは2日~15日までの間に行うのが一般的だといわれていますが、日記の中では正月~2月の20日間あまりにわたって年礼を受け、また年礼に出掛けています。3月や4月に年礼に出掛けた年もあり、彼の交際範囲の広さがうかがえます。
年玉の品は、年賀に限らず広く贈答品として使われた扇子と手拭が圧倒的に多く、他は日用品や嗜好品で、かさの小さいものです。
医者が年玉として薬を贈ったり、当初は珍しかった菓子や茶などの嗜好品が、年を追って増加する点など、日記の中で年玉の品とその微妙な変遷に幕末の時流を感じることができます。
三右衛門日記にみる国定忠治
嘉永3年(1850)12月21日博徒(ばくと)(ばくち打ち)島村の伊三郎殺し、大戸(現東吾妻町)の関所破り、道案内三室の勘助殺しの罪で関東取締出役(とりしまりしゅつやく)(八州廻り)の指名手配を受けていた博徒国定忠治(本名長岡忠次郎)は、ついに捕まり、大戸で磔(はりつけ)となりました。
後に、演劇や映画で取り上げられヒ−ロ−伝説となった忠治は確かに存在し、三右衛門日記にも登場しています。
嘉永3年8月24日、関東取締出役中山誠一郎は田部井村(ためがいむら)(現伊勢崎市)で中風を発病していた忠治を捕らえます。その一ヶ月後の9月28日の大雨の日、捕らえられた子分や妾とともに忠治は玉村宿へ連行され、10月15日江戸へ向けて立つまでの17日間留置されました。このまれにみる大物囚人一行にかかる警備人員の動員や取調べを行う役人の賄いにかかる経費は三右衛門が大惣代を勤める組合村にとっては大変な負担となりました。
ところで、忠治とともに連行された忠治の妾トクと三右衛門は江戸で再会します。トクは30日間の外出禁止の刑を受けた後、嫁いだ先の五目牛(ごめうし)村(現伊勢崎市)に戻り、大地主として成功をおさめました。三右衛門はトクの後見人となりますが、その後三行半(みくだりはん)(離縁状)を出します。
幕末の才人
千輝玉斎(ちぎらぎょくさい)
江戸時代後期に活躍した絵師です。寛政2年(1790)吾妻郡中之条町に生まれました。24歳のとき中之条を離れ、その後玉村宿上新田村の旅籠屋萬屋(仙蔵娘ゑい)に婿入りしました。通称は幸兵衛または幸吉といい、「玉斎」は玉村にちなんだ雅号です。幼い頃から絵画を好み、人々を驚かせたといわれていますが、家業に余裕ができるとともに画の道に励み、技を磨き才能を開花させました。
玉斎が活躍した文化・文政期以降(1804年~)の日本は、江戸町民を中心とした民衆文化の時代であると同時に、活発となった三都(江戸・京都・大坂)との交流から、中央の文化が周辺に伝播し、地方にも文化人のサ−クルが結成されていく時代でした。
絵画では、外国からの影響を受けて発生した文人画や写生画が黄金期を迎えるとともに、江戸の庶民絵画浮世絵が、強烈な刺激を伴って全盛を迎えました。玉斎の絵画にもこれらの影響が認められ、特に彼の描く人物は、伸びやかな描線や動きのある豊かな表情を特徴としています。また、彼の才能は茶道や生花、彫刻など多方面にわたりました。庭には、「玉斎楼」といわれる茶室があったといわれています。
天保期(1830年~)になると、文人同志の交流が活発となり、合作も生まれました。明治2年(1869)頃には、中之条町において玉斎が書画の展覧会を開催し、大評判になったことが伝えられています。玉斎の足跡は、地元玉村町だけでなく、生地である中之条町にも断片的ながら、その作品とともに多く残されています。
千輝玉斎は、明治5年(1872)6月9日、83歳で没しました。戒名「仁誉鶴翁玉斎居士」、墓は玉村町下新田の称念寺にあります。
作品には、新町の飯売下女9人が新町八幡宮に奉納した絵馬「紅葉狩」、観照寺(玉村町上之手)・火雷神社(玉村町下之宮)の天井画、稲作の様子を順序立てて描いた襖絵「豊年満作之図」、橋上に百人ほどの人物が描かれた襖絵「橋上人物百態図」、屏風「蘭亭曲水宴図」などがあります。
同時代の絵師には、神楽寺(玉村町下新田)住職碧潭(へきたん)(伝海)や玉村宿下新田村7丁目に住み、宿役人も勤め渡辺三右衛門の酒の友であった柴田雲がい(うんがい)がいます。

屏風「琴棋書画集会之図」慶応元年(1865)
藤枝太郎英義(ふじえだたろうてるよし)
藤枝太郎英義(繁太郎・治廣とも名乗る)は、上野国那波郡川井村(現玉村町川井)出身の江戸時代末期に活躍した刀工です。父は刀工の玉鱗子英一、母は高崎藩の儒臣江積積善の娘みゑで、文政6年(1823)6月7日に生まれました。
父英一(政右衛門・政之進とも名乗る。寛政元年~嘉永4年)は、高崎藩のお抱え刀工であった小島震鱗子克一の下で修業し、また江積積善に学問を学びました。英一の本姓は鈴木氏でしたが、後に養子英二(鉄砲鍛冶)に家督を譲り、天保8年(1837)49歳で、妻と長男英義・次男英利(鈴藤勇次郎。勝海舟らとともに軍艦咸臨丸で太平洋横断をし咸臨丸の絵も描いた)・三男英興(父の跡を継ぎ鉄砲鍛冶となる)の3人の子とともに代々鉄砲鍛冶であった川越藩士藤枝家を継ぎ藤枝姓に改め、川越藩に仕えました。
英義は、父の下で修業した後、各地で修業を積み、そのなかで細川正義の門に入りました。
嘉永4年(1851)4月、父英一の死去にともない藤枝家を継ぎ、同時に川越藩のお抱え刀工となりました。英義は始め川越に住んでいましたが、その後江戸に移り、幕末の外国船の渡来に備え武備の増強が急がれたことから長巻・刀・薙刀それぞれ二百振の作刀を行いました。
慶応2年(1866)川越藩が前橋に移り、さらに江戸幕府が倒れ明治時代になると世の中の様子も変わっていきました。英義もそのような中で、江戸から前橋に移り、明治4年(1871)10月には郷里近くの飯倉村(現玉村町飯倉)の慈恩寺に住むようになりました。そこで、農具を作ったり、村人の相談や調停役をしていましたが、明治9年(1876)廃刀令が出された同じ年の5月24日、54歳でこの世を去りました。戒名「賢光院英義居士」。

藤枝太郎英義秘伝書(藤枝英義著)個人寄託
安政3年(1856)
英義の門人正木英辰に与えるため書かれた。

玉村町指定重要文化財
脇指:火雷神社寄託
銘:(表)応和田□之需藤枝英義作之
(裏)従一位火雷大神翦刀
明治六酉年八月吉日
長さ:37.1cm、反り:0.9cm
英義最晩年の火雷神社に奉納した脇指