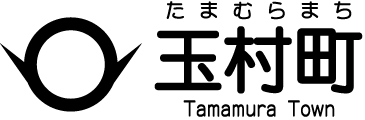公開日 2025年07月31日
納税が困難で一定の要件に該当する場合は、申請いただくことで「徴収猶予」又は「換価の猶予」という納税の猶予制度を利用することができます。
徴収猶予
徴収猶予 (※根拠法令:地方税法第15条第1項)
条件
例えば以下のようなケースに該当し、一時に町税等を納税することが困難な方が対象となります。
・納税者が営む事業について、著しい損失が生じた場合
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
・納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
・納税者が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した場合 など
対象となる税
全ての町税(町県民税、固定資産税等)及び介護保険料、後期高齢者医療保険料
猶予期間
最長1年間
延滞金
猶予に該当する事実が災害、盗難、病気、負傷又はこれらに類似する場合は、猶予期間中の延滞金の全額が免除されます。
また、猶予に該当する事実が事業の休廃止、事業上の著しい損失又はこれらに類似する場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除になります。具体的には、猶予特例基準割合を超える分(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年1.5%、それ以降は年7.8%)が免除されます。例えば、令和7年中の場合、延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.4%、それ以降が年8.7%で計算されますが、猶予特例基準割合を超える分が免除され、残りの年0.9%分の延滞金をご納付いただくことになります。
納付方法
猶予期間内での分割納付
担保
担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。 ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。
地方税法により担保として提供できる財産の種類には、主に次のようなものがあります。
① 国債や町長が確実と認める上場株式などの有価証券
② 土地、保険に付した建物
③ 町長が確実と認める保証人の保証
申請期限
原則、納期限までにご申請ください。納期限後の申請の場合は、督促状等が送付されることがあります。
納税通知書が発送されて以後、または、町税を申告されて以後に、ご申請ください。
申請様式
申請様式
以下の書類が必要となります。申請様式については税務課収納特別対策係へお問い合わせください。
①徴収猶予申請書
②財産収支に係る書類
(a) 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合⇒財産収支状況書
(b) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合⇒財産目録、収支の明細書
③猶予に該当する事実があることを証する書類
猶予に該当する事実(上記の「条件」欄を参照)についての支出が分かる領収証書などのコピー、売上などの減少が分かる売上帳や預金通帳などのコピーをご提出ください。 なお、猶予に該当する事実が「納税者の事業について著しい損失が生じた場合」である場合は、法人においては、直近2年度分の損益計算書、個人においては、直近2年分の確定申告書のコピーなどをご提出ください。
④担保提供に必要な書類(担保提供が必要となる場合のみ)
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、担保提供が必要となる場合は、①~③の書類をご提出いただいた後に、担保提供に必要な書類等についてご案内いたします。
※審査にあたり、電話にて申請内容の確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
猶予期間の延長
やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。
猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに(概ね1か月前)以下の書類の提出が必要となります。
①徴収猶予期間延長申請書
②財産収支に係る書類
(a) 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合⇒財産収支状況書
(b) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合⇒財産目録、収支の明細書
換価の猶予
申請による換価の猶予 (※根拠法令:地方税法第15条の6)
条件
町税等を一時に納税することによって、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある方が対象となります。
対象となる税
全ての町税(町県民税、固定資産税等)及び介護保険料、後期高齢者医療保険料
猶予期間
最長1年間
延滞金
猶予期間中の延滞金は、一部が免除されます。具体的には、猶予特例基準割合を越える分(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年1.5%、それ以降は年7.8%)が免除されます。例えば、令和7年中の場合、延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.4%、それ以降が年8.7%で計算されますが、猶予特例基準割合を超える分が免除され、残りの年0.9%分の延滞金をご納付いただくことになります。
納付方法
猶予期間内での分割納付
担保
担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。
地方税法により担保として提供できる財産の種類には、主に次のようなものがあります。
① 国債や町長が確実と認める上場株式などの有価証券
② 土地、保険に付した建物
③ 町長が確実と認める保証人の保証
申請期限
町税等の納期限から3か月以内にご申請ください。法人町民税など申告が必要な町税の場合は、申告後にご申請ください。
納期限後に審査を行う制度となりますので、年間に複数の納期限がある町税(町県民税、固定資産税等)の場合、納期限の都度、申請が必要となります。換価の猶予を申請された場合でも、納期限後に督促状が送付されますので、ご容赦ください。
申請様式
以下の書類が必要となります。申請様式については税務課収納特別対策係へお問い合わせください。
①換価の猶予申請書
②財産収支に係る書類
(a) 猶予を受けようとする金額が50万円未満⇒ご提出は不要です。
(b) 猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満⇒その他の財産収支状況書
(c) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合⇒財産目録、収支の明細書
③担保提供に必要な書類(担保が必要となる場合のみ)
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、担保提供が必要となる場合は、①~②の書類をご提出いただいた後に、担保提供に必要な書類等についてご案内いたします。
※審査にあたり、電話にて申請内容の確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
猶予期間の延長
やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。
猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに(概ね1か月前)、以下の書類をご提出ください。
①換価の猶予期間延長申請書
②財産収支に係る書類
(a) 猶予を受けようとする金額が50万円未満⇒ご提出は不要です。
(b) 猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満⇒その他の財産収支状況書
(c) 猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合⇒財産目録、収支の明細書
猶予の手続きの流れ
①「徴収猶予」又は「換価の猶予」の申請書類を記入し、税務課収納特別対策係へ提出していただきます。
②必要書類を受領後、審査を行います。審査にあたり、お電話で申請書類の記載内容についてお伺いすることもありますので、ご協力ください。猶予を受けようとする金額が100万円を超え、担保提供が必要となる場合は、お手続き等についてご案内いたします。審査等の手続きにかかかる日数は、数日~20日程度で見込んでおりますが、申請状況によっては、日数を要することもございますので、ご了承ください。
③猶予決定の通知書(又は不許可の通知書)と新たな納付書を郵便にて申請者の方に送付します。
④猶予の決定後は、猶予決定の通知書に記載している納付計画のとおり 、新たに送付した納付書にてご納付してください。
申請先・問い合わせ先
玉村町税務課収納特別対策係
〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL 0270-64-7704
FAX 0270-65-2592
メールアドレス tainouseiri@town.tamamura.lg.jp