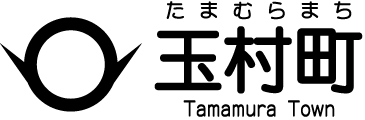公開日 2024年04月03日
更新日 2025年04月23日
国民健康保険税(国保税)について
みんなで支える国民健康保険
みなさんが病院などで診療を受けると、かかった医療費の一部を病院などの窓口で支払います。
残りの医療費は、皆さんが納めた国保税、国や県の補助金、玉村町の繰入金などでまかなわれる仕組みになっています。国保税は医療費の大切な財源になっています。
納税義務者は世帯主
世帯主の方が国保に加入していなくとも、同一世帯内のどなたかが、国保に加入していれば、世帯主が納税義務者になります。後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入する75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方で、後期高齢者医療制度に移行された方を含む)が世帯主の場合もその世帯主が納税義務者です。
この場合、国保に加入していない世帯主の所得金額に関する割合は計算には含まれません。(ただし、軽減判定には世帯主の所得金額も含まれます。)
令和7年度 国民健康保険税の税率等
医療分と後期高齢者支援金分と介護分の合計額を国保税として納付します。加入者全員の所得金額などから計算します。医療分と支援金分と介護分でそれぞれ納める額の上限が定められています。
※令和7年度は税率と上限額が変更になりました。
医療分
下の表で計算した合計額が、国保税の医療分となります。ただし、合計した結果が66万円を超えるときは66万円分を医療分とします。
※所得には遺族年金、障害年金、失業給付金は含みません。退職金は含みませんが、退職金を年金方式で受け取る場合「公的年金等」の収入と同じ扱いになりますので、その場合は含まれます。
| 区分 | 計算方法 | |
|---|---|---|
| 所得割額 | 所得に応じた額 |
(前年の総所得金額等-基礎控除(43万円))×7.0% |
| 均等割額 | 加入者数に応じた額 |
29,500円×加入者数 |
| 平等割額 | 世帯ごとに定額の額 | 23,000円 1世帯につき |
支援金分
下の表で計算した合計額が、国保税の支援金分となります。ただし、合計した結果が26万円を超えるときは26万円分を支援金分とします。
※所得には遺族年金、障害年金、失業給付金は含みません。退職金は含みませんが、退職金を年金方式で受け取る場合「公的年金等」の収入と同じ 扱いになりますので、その場合は含まれます。
| 区分 | 計算方法 | |
|---|---|---|
| 所得割額 | 所得に応じた額 |
(前年の総所得金額等-基礎控除(43万円))×3.0% |
| 均等割額 | 加入者に応じた額 | 11,500円×加入者数 |
| 平等割額 | 世帯ごとに定額の額 | 9,000円 1世帯につき |
介護分
玉村町の国民健康保険の加入者のうち、40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料も一緒に納めていただきます。下の表で計算した合計額が、介護分となります。ただし、合計した結果が17万円を超えるときは17万円分を介護分とします。
※所得には遺族年金、障害年金、失業給付金は含みません。退職金は含みませんが、退職金を年金方式で受け取る場合「公的年金等」の収入と同じ扱いになりますので、その場合は含まれます。
| 区分 | 計算方法 | |
|---|---|---|
| 所得割額 | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じた額 |
(前年の総所得金額等-基礎控除(43万円))×2.7% |
| 均等割額 | 40歳から64歳までの加入者の所得に応じた額 | 10,000円×加入者数 |
| 平等割額 | 世帯ごとに定額の額 | 8,000円 1世帯につき |
◎年度の途中で国保に入ったり、国保から抜けたりする場合
年度途中で加入された場合は、加入された月(手続きした月ではありません)から翌年3月(年度末)までの加入月数で税額を計算し、これから到来する納期の回数に割り振って納めていただきます。
年度途中で国保から抜けた場合は、その前月までの加入月数で税額を計算し、精算を行います。
加入月数で計算した税額が納付済み額を超える場合は、不足分の納税通知書をお送りします。既に納期限を過ぎているものの納期限は当初どおりです。
加入月数で計算した税額より納付済み額が多い場合は、超過分を還付します。未納の町税がある場合は、その分に充当されます。
◎年度の途中で40歳になる人の国保税
40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前の月)分からの月数分の介護分を合わせて納めます。
◎年度の途中で65歳になる人の国保税
65歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前)の前の月分までの月数分の介護分を合わせて納めます。
◎年度の途中で75歳になる人の国保税
75歳の誕生日のある月の前の月分まで国保加入者ですので加入月割分を納めます。 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。
軽減制度
加入者と世帯主(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年の所得金額の合計額が一定金額以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減されます(下記の計算式参照)。軽減措置は、前年所得の申告が済んでいれば、自動で判定されます。軽減に申請は必要ありませんが、加入者と世帯主の中に所得の申告が済んでいない人がいると軽減は適用されません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得の方も、町・県民税又は国民健康保険税の申告が必要です。前年の収入について申告が済んでいない方は、申告書の提出をお願いします。
| 7割軽減 | 総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈1> の数-1)以下 |
|---|---|
| 5割軽減 | 総所得金額等が43万円+(30.5万円×被保険者数<注釈2>)+10万円×(給与所得者等<注釈1>の数-1)以下 |
| 2割軽減 |
総所得金額等が43万円+(56万円×被保険者数<注釈2>)+10万円×(給与所得者等<注釈1>の数-1)以下 |
- 注釈1 給与所得者等とは、給与収入55万円を超える給与所得者及び65歳未満の場合は公的年金等の収入が60万円を超える公的年金所得者と、65歳以上の場合は公的年金等の収入が125万円を超える公的年金所得者の方を指します。
- 注釈2 被保険者数には、被保険者及び同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
- 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです)
- 賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。
非自発的失業(離職)者に対する軽減制度
非自発的失業(離職)者に対する保険税の軽減制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。非自発的失業(離職)者に対する軽減制度のページ
国民健康保険税の納税通知
7月に納税通知書をお送りします
玉村町では、所得割額の基となる前年分の総所得の決定後に国保税額を計算し、納税通知書により税額及び納期限をお知らせします。課税算出基礎、年税額、期別額、納付方法等が書かれています。よくご確認ください。
納期(7月から翌年2月までの8回)と納付方法(普通徴収のみの場合)
納付書や口座振替で納付することを普通徴収といいます。

65歳から74歳の、国民健康保険に加入する世帯主は、国保税が年金から徴収される可能性があります
年金からの天引きにより国保税を収める方法を特別徴収といいます。
特別徴収は次のすべての条件に当てはまる方が対象となります。ただし、他市町村から転入して玉村町国民健康保険に加入した場合や、年金からの借入れがある場合など、すぐには特別徴収が開始できないことがあります。なお、条件に該当しない場合は、従来どおり口座振替または納付書による普通徴収となります。
※複数の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金など)を受給中の場合は優先順位があり、優先順位の高い年金から天引きされます。
※国保税は介護保険料が特別徴収をしている場合に、同じ年金から天引きされます。そのため、介護保険料が特別徴収とならない場合には国保税も特別徴収にはなりません。
■特別徴収の該当条件
1.世帯主が国民健康保険の加入者であること
2.世帯の国保加入者全員の年齢が65歳以上であること
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
4.世帯主の介護保険料が特別徴収であること
5.介護保険料と国保税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収(年金からの天引き)は4月から開始されます。
当該年度の4月から、特別徴収(年金の天引き)が始まります。仮徴収として前年度の2月に天引きされた額と同額が4月、6月、8月の年金から天引きされます。7月の本算定により決定した当該年度の国保税から仮徴収として天引きされた額を差し引いた額が10月、12月、2月の年金から天引きとなります。

また、6月、8月、10月から特別徴収が開始となる方もいますが、該当者の方には改めて通知をさせていただきます。
特別徴収から普通徴収への切り替え、特別徴収のほかに普通徴収でも納付が発生する場合
次の条件に該当すると、特別徴収から普通徴収に切り替えになる場合があります。
■特別徴収から普通徴収に切り替わる条件
1.世帯主が75歳に到達する年度
世帯主が年度途中で75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するため、その年度について特別徴収は行えません。
2.特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届出をしたとき
口座振替に変更後、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に特別徴収に変更になる場合があります。
3.特別徴収の条件を満たさなくなったとき(世帯主が転出、国民健康保険の脱退、死亡したときなど、上記の「特別徴収の該当条件」を満たさなくなったとき)
該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国保税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国保税を普通徴収で納付していただきます。
4.資格異動、国保税更正等により国保税が増額または減額となったとき
該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国保税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国保税を普通徴収で納付していただきます。
5.年金の受給権を担保に借入れしているとき
該当年度の特別徴収を停止(中止)し、特別徴収できなかった国保税を含め、普通徴収の残りの納期で再度期割します。期割の国保税を普通徴収で納付していただきます。
6.年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国保税を天引きできないとき
納期で再度期割りします。期割の国保税を普通徴収で納付していただきます。
Q&A
Q:主人は社会保険で国保には息子だけが加入しています。なのに主人あてに国保の納税通知書が届きました。どうして?
- A:国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険でも家族が国民健康保険に加入している場合、世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます)
このため世帯主のご主人様あてに納税通知書をお送りしました。税額の算出は国保に加入している息子さんの分だけで、ご主人様の分は含まれていません。
Q:無収入の申告をしたのですが、国保税がかかるのはなぜですか?
- A:国民健康保険税は加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と、加入している人数に応じて決まる部分(応益部分)があり、所得の無い方については応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割、平等割)は課税されます。
※世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い方や一定所得以下の方には7割、5割、2割の軽減措置がされますが、その場合でも無税となることはありません。
Q:今は国保にだれも加入していないのに納税通知書が届いた。どうして?
- A:4月から6月の間に、国保に加入し、その後脱退の届出をしていませんか。たとえば4月に社会保険をやめ国保に入り、6月には国保をやめ社会保険に入ったときなど。このような場合には、国保に入っていた4月から5月分の国保税として7月に納税通知書をお送りします。